人はなぜ「食べる」ことに救われるのか。
朝ドラ『あんぱん』は、
単なるグルメや食事風景ではなく、
“食べる”という行為の深い意味を描いている。
このテーマは、
やなせたかしが生涯を通して語り続けたメッセージとも重なっている。
この記事では、
「食べること」=「生きること」という視点から、作品に通底する哲学を考察する。
この記事を読むとわかること
- 『あんぱん』に描かれる“食べること”の意味
- やなせたかし作品とのテーマ的共通点
- 「あげる」ではなく「分けあう」という価値観
- “食べる”を通して描かれる人間のつながり
1. 空腹は、心も蝕む
『あんぱん』の中には、
「おなかをすかせた子ども」や「何も食べずに働く若者」など、
食を巡るさまざまな人物が登場する。
■ 食べ物の欠如=希望の欠如
“食べられない”ことは、
単に体力を失うだけではなく、
「生きる力」をゆっくり奪っていく。
そこに、やなせが戦争体験から得た実感がにじむ。
2. あたたかい食事は、希望になる
空腹の人に、食べものを差し出す。
たったそれだけのことが、
人生を変えるきっかけになる。
■「あんぱんを届ける」という行為
劇中で誰かがあんぱんを渡す瞬間は、
「ただの食事」ではなく、
生きる意味をもう一度与える行為として描かれている。
3. 「あげる」ではなく「分けあう」
『あんぱん』の中で印象的なのは、
登場人物たちが“あげる”のではなく、“分けあう”という姿勢を見せていることだ。
そこには、やなせたかしがアンパンマンに込めた思想──
「自分の顔をちぎって与える」という、究極の献身と共感が重なる。
■ 自分の痛みを知っているから、差し出せる
“分けあう”ことができる人は、
自らも空腹や孤独を知っている。
『あんぱん』に登場するキャラクターたちは、
その経験を経て「誰かに差し出せる心」を育ててきたのだ。
4. まとめ|食べることは、生きること
「食べることは、生きること」
──やなせたかしが作品を通じて伝え続けたこのメッセージは、
『あんぱん』という物語の核でもある。
体を満たすだけでなく、
心を満たし、希望を育てる。
あたたかい食べものを通じて、誰かとつながる。
そんな「日常の中の救い」が、
本作のいたるところに描かれている。
そしてそれは、
現代を生きる私たちにも、そっと寄り添ってくれるのだ。
最後までお読み下さりありがとうございました。
この記事のまとめ
- 『あんぱん』は“食べること”を通じて生きる意味を描いている
- やなせ作品と共通する「分けあう心」が根底にある
- 空腹や孤独を知る人ほど、誰かを助ける力を持っている
- あたたかい食卓が、人を救うという普遍的なテーマが描かれている

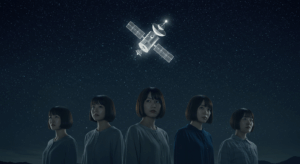
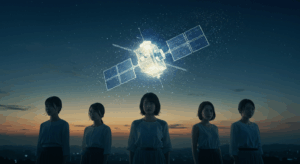
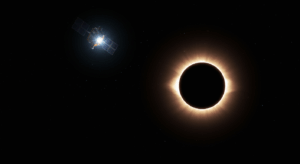
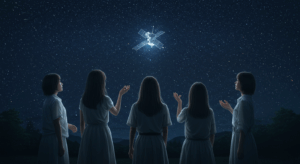
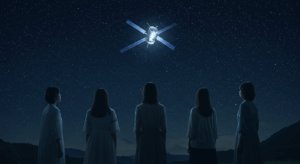
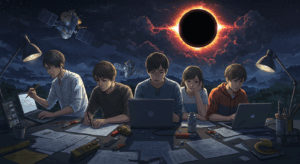
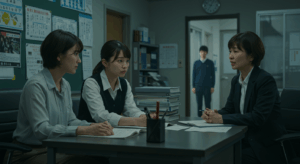

コメント