ドラマ『彼女がそれも愛と呼ぶなら』は、明確なセリフや感情の爆発ではなく、「静けさ」と「余白」によって心の機微を描く異色の作品である。その背景には、演出家・塚原あゆ子氏と撮影監督・安藝孝仁氏という、数々の名作を共に手がけてきた黄金コンビの存在がある。
この記事を読むとわかること
- ドラマ『彼女がそれも愛と呼ぶなら』における演出と映像表現の特徴
- 演出家・塚原あゆ子氏の演出スタイルと美学
- 撮影監督・安藝孝仁氏の撮影哲学と映像へのこだわり
- 「静かな熱量」や「余白の美学」が映像にどう活かされているか
- 過去作との比較から見る本作の進化と表現の深化
「語らない演出」で物語を深める塚原あゆ子の演出術
塚原氏が本作で特に意識したのは、登場人物の“語らぬ感情”をどう映像で表現するかという点である。
「視聴者が感じ取れる“余地”を残すことで、作品はより豊かになる。説明しすぎないことが、ドラマの奥行きを生む」
彼女の言葉には、確固たる美学が滲む。
実際、第3話のワンシーン──互いに背を向けて立ち尽くす主人公たちの姿──では、セリフはほとんど交わされない。それでも画面からは、過去の痛みや赦しの萌芽が伝わってくる。塚原演出の真骨頂である。
安藝孝仁が映し出す「感情の余白」
一方、撮影を担当する安藝孝仁氏は、本作でも“画づくり”の静謐さを極限まで追求している。
「すべてを映さないことで、観る人に“想像させる”空間が生まれる。それが映像の醍醐味だと思う」
ロングショットで切り取られる広い室内や、窓から差し込む光の変化。その一つひとつが、感情の“陰”を語る手段として機能している。特に、物語終盤の橋の上のシーンでは、逆光の中に立つ人物のシルエットだけで「赦し」「喪失」「再生」を描いているようにさえ感じられる。
チームワークが映像に宿す“熱量”
塚原氏と安藝氏は、これまでも『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』といったTBSドラマで共にタッグを組み、独自の映像世界を構築してきた。今回もその信頼関係は健在で、脚本の段階から「絵のトーン」や「カット割りの呼吸感」を共有しながら準備が進められたという。
「リハーサルの時点で“これ以上カメラを入れない”と決める瞬間がある。あとは役者の感情に任せて、そっと見守る」──塚原あゆ子
演者が自由に感情を動かし、それをカメラが捉える。この有機的な連携こそが、本作の映像に“静かな熱量”を宿している理由なのだ。
過去作との比較が示す進化
たとえば『最愛』では、人物の心の動きをクローズアップで捉えることで、感情の揺らぎを視覚的に伝えていたが、本作ではそれがさらに進化し、「カメラを引くことで感情を感じさせる」という引き算の美学へと昇華している。
同じ演出・撮影のタッグながら、物語に応じて“語り方”を変化させる柔軟さと、緻密な映像設計力がうかがえる。
まとめ:静かなる映像美、その先にあるもの
『彼女がそれも愛と呼ぶなら』は、明確な答えを提示するドラマではない。
だが、塚原あゆ子と安藝孝仁という名匠たちが生み出した“静けさ”の中には、視聴者一人ひとりの心を震わせるだけの豊かさが詰まっている。
この作品を観終えたあと、何気ない沈黙や風景に、私たちはきっと新たな意味を見出すだろう。
この記事のまとめ
- 『彼女がそれも愛と呼ぶなら』は、静けさと余白で感情を描く演出が特徴のドラマ。
- 演出家・塚原あゆ子氏は「語らない演出」によって登場人物の内面を浮かび上がらせている。
- 撮影監督・安藝孝仁氏は光と影、空間の余白を使って映像に深みを与えている。
- 過去作『最愛』『MIU404』などの映像哲学が、本作でもさらに進化して表現されている。
- 演出と撮影の緊密なチームワークが、視聴者の心を動かす“静かな熱量”を映像に宿している。




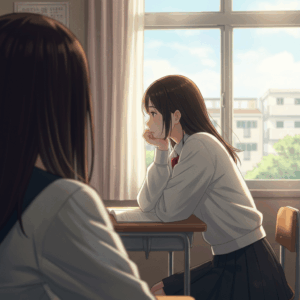




コメント